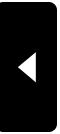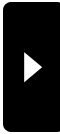2019年07月23日 21:02







てるる41弦制作≫
久々の投稿となりました。
何をしていたかと言えば、ひたすら甲の成形です。
気付けば朝も昼も夜も・・・
ふくらみを持ったアーチトップの竪琴は
世界中でてるる詩の木工房だけが制作しています。
表面だけではなく、見えない内側の削りにも長い時間をかけます。
完成したときの音を予感させるような響きが
削りながら立ち上ってくるようになります。
それぞれに内側の形から『太陽のしずく』『星月夜』と名前が付きました☆
ご注文を頂いている総桑の楽器。
ゆっくりと果実が熟するように形が出来上がっていきます。
完成まであと一息!

煮詰まりそうなこんな時、海辺を散歩するのが良い気分転換。
先日の散歩中、海の向こうから網袋を重そうに持ってくる男性が・・・
なんとサルボウガイがいっぱい!
採り方を教えてもらい、次の日私たちも挑戦してみました!

砂の中で口を開いているのが見えるので、
棒でつつくとふっと砂を吐く、そこを掘り起こすというシンプルな漁。
目をこらして見つけました!

天使の羽根のような殻。
蝶番の仕組みも本当に精緻で美しい。
自然の美しい形から学ぶことはたくさんあります。
ゆっくりゆっくり自らの殻を成長させていく姿に甲を少しずつ削る姿が重なります。

自分で採った味は格別です!
たくさんの夏野菜と一緒にいただきました。
2019年06月30日 10:03

沖縄地方はとうとう梅雨が明けました!
数日前の雨が嘘のような青天です。
次男の梅仕事も順調に進行中。
梅を漬けていた容器を開くと濃厚な梅の香が
広がっていましたが今日は日差しの香り。
澄んだ夏の光が部屋の隅まで届いています。
夏至南風(カーチーベー)もふんわり入ってきます。
先日梅雨の中あやはべる9弦をご購入されたU様から
素敵な動画をいただきました。
ほたる〜ナミノコ(あやはべる9弦)
森羅万象に響きあう、祈りのようなうた声と音色です。
ほたるの輝きと自分の心の中の光が呼応しあい、
共鳴し合っているような、、、
小さな命の輝きに想いを馳せ耳を澄まして
どうぞお聴きください。

竪琴の音色≫
カテゴリー │楽器制作│あやはべる│てるる詩の木工房│movie│Onlineshop

沖縄地方はとうとう梅雨が明けました!
数日前の雨が嘘のような青天です。
次男の梅仕事も順調に進行中。
梅を漬けていた容器を開くと濃厚な梅の香が
広がっていましたが今日は日差しの香り。
澄んだ夏の光が部屋の隅まで届いています。
夏至南風(カーチーベー)もふんわり入ってきます。
先日梅雨の中あやはべる9弦をご購入されたU様から
素敵な動画をいただきました。
ほたる〜ナミノコ(あやはべる9弦)
森羅万象に響きあう、祈りのようなうた声と音色です。
ほたるの輝きと自分の心の中の光が呼応しあい、
共鳴し合っているような、、、
小さな命の輝きに想いを馳せ耳を澄まして
どうぞお聴きください。

2019年06月22日 15:07
 6月22日の今日は夏至です。
6月22日の今日は夏至です。
この日より、てるる詩の木工房のOnlineshop をopen致します。
てるる詩の木工房Onlineshop
これまで個々にご紹介していた楽器をまとまった形で
ご覧になることができます。
お支払い方法もクレジットカード、コンビニ決済、翌月後払い、PayPal、等が
ご使用になれるようになりました。
また、現在制作中の楽器を予約できるようになりました。

Onlineshopのお知らせ≫
カテゴリー │Onlineshop

この日より、てるる詩の木工房のOnlineshop をopen致します。
てるる詩の木工房Onlineshop
これまで個々にご紹介していた楽器をまとまった形で
ご覧になることができます。
お支払い方法もクレジットカード、コンビニ決済、翌月後払い、PayPal、等が
ご使用になれるようになりました。
また、現在制作中の楽器を予約できるようになりました。
皆様の心の琴線にふれる楽器となるよう、
これからも精進を続けていきたいと思っております。
どうぞよろしくお願い致します。

梅雨空に咲く、ファイアーボールリリー。
毎年季節を忘れず、夏至の頃突然咲きます!
いにしえの人々はこの頃に吹く南風
(夏至南風・カーチーベー)にのって船旅に出ました。
船出にあたり、うたをうたって航海の安全を寿ぎ祈りました。
留守中も節目節目で旅に出ている家族の安全を
皆で集まり、輪になって歌い願ったのです。
だんじゅ嘉利吉や (なんとおめでたいことか)
選でさしめしたる (佳き日を選んで)
御船の綱取れば (船の綱をとれば)
風やまとも (必ずよき風が吹いてきます)
だんじゅかりゆしより
梅雨から明けて晴れ渡った青空に
広い海へと漕ぎ出す船、
そして清々しい風を感じながら
太鼓の音と祈りのうたごえに送られる様子が目に浮かびます。
現在と違って簡単に連絡も出来ず、危険も伴う長い決死の船旅、
その安全をうたにのせて祈り願ったひとびとの思いに何度聴いても感動します。
2019年06月04日 21:55





旧5月1日生まれのあやはべる9弦≫

6月3日は旧5月1日、新月でした。
この日、新しく生まれた竪琴に弦を張りました。
梅雨の合間に青空が広がっていました!
今回は3種類の木で制作しています。
くすの木、ヒノキ、ヤマクルチです。ヒノキ以外は沖縄の木です。
いずれも香る木、制作中工房の中に木を削る良い香りが立ちこめていました。
それぞれご紹介します☆

ヒノキ・・・『日の木』、とも呼ばれる木です。
最高級の日本建築や、仏像の素材としても用いられました。
目の詰んで通った柾目、かつてはバイオリンに使用されたこともあったそうです。
温かみがあり、クリアーな音質です。
制作中は針葉樹独特のすうっとした香りでした。

ヤマクルチ・・・『山の黒い木』という意。
今回制作した中で最も軽く、450gでした。
狂いが少なく丈夫で、指物に使用される木です。
弦の振動を良く伝え、明るい音質です。
バニラ系の香りがあり、チョコチップクッキーのような香ばしい香りでした。
(ちなみに切ったり削ったりと加工中の香りで、完成品からは香りはしません)

くすの木・・・虹色の木目を持つ木、と言われています。
同じ木から製材してもそれぞれが個性豊かです。
きめが細かく、丈夫な木です。
木魚はくすの木で作るとまろやかな音がするそうです。
ご神木、として各地に大木が生えています。トトロもくすの木の精でした。
精油成分が多く、木の下を通るだけでカンファーの良い香りがします。
この木を加工中に工房を訪れた方は皆『良い香りがしますね!私、木の香り大好きです!』と仰います。
つややかで明るい音質です。
あやはべる9弦 ペンタトニック
¥45000(税込み価格)
*調弦器・冊子『竪琴の物語』・紙ケース付き
*送料は別途となります。(関東圏:¥1879)
あやはべる9弦 ペンタトニック・スターターキット
¥48000(税込み価格)
*調弦器・冊子『竪琴の物語』・紙ケースの上記基本セットに加え、
電子チューナー、曲集『ちいさな竪琴と歌う季節の歌』知花洋子著が
ついています。すぐに竪琴を始めたい方にとってお得で便利なセットです。
*送料は別途となります。(関東圏:¥1879)
今回からお支払い方法が、銀行口座お振り込みに加え、
便利なPaypalをご利用できるようになりました。
2019年05月16日 21:35










桑の木の竪琴≫
カテゴリー │楽器制作│あやはべる│てるる│てるる詩の木工房
奄美に続き沖縄地方も梅雨入りしました。
雨の日は集中できるので好きです。
お陰様であやはべる9弦初回限定20台は完売致しました。
心より御礼申し上げます。
現在新たな制作に取りかかっています。
ご注文頂いている桑製のてるる41弦。
わらび手の削り、それから甲の削りを行っています。
あやはべる9弦、今回はクスノキ、ヒノキ、伊集、ヤマクルチ、イエローシーダーの
各材木で制作中。前回から改良し、新たな試みも行っています。
あやはべる9弦はいずれもご予約可能です。
それぞれにどんな音がするのか楽しみです。
甲を削る、指先ほどの豆かんな。
あんまり小さいのでかんなのミニチュアと間違えられたこともありますが、
ちゃんとした道具です。
竪琴の表面板のバイオリンの様なふくらみはこの小さいかんなで形作っていきます。

荒い砥石から数種類の砥石を使って刃を研ぎます。
右はまだ使って間もない新しいかんな。
左は研いで小さくなった刃。台も何度か作り直して使い勝手を良くしています。
良く研いだ刃はまるで自分の手の延長のように気持ちよく木を形作っていきます。
甲の柔らかな曲線が、うたうような音を作り出します。
実はアーチトップの竪琴は世界中でてるる詩の木工房だけしか作っていません。
フラットトップの3倍以上の厚みの木を削りだしてふくらみを作るのには
とても時間と集中力を必要とする作業です。
削っているときも音が変わってくるのがわかります。
楽器の音を決める大切な工程です。

ちょうど『海止め山止め』の季節。
自然界の小さな命が育まれる時期なので
海山で何かを採ること、大きな音を出すことが禁じられます。
命を育む時期は静かに慈しむ時間。
しばらくは工房でも作業に向かう静かな時間が続きそうです。
2019年05月05日 19:47






旧3月15日生まれのあやはべる9弦≫
今日は旧4月1日新月。
遅ればせながら4月19日、旧3月15日にあやはべる9弦が完成しました。
お陰様で初回限定20台のうち、残り2台となりました。
ご予約頂いた皆様には心より御礼申し上げます。
今回までは本体はトネリコ材、
表甲は新月バージョンがスプルース、
満月バージョンがレッドシーダーです。
※2台ご注文された方には新月&満月をお届けいたします。
音に直接触れる、サドルは貴重な沖縄県産桑材、
ブリッジ、ナットは三線の棹にも使用するユシギ材です。
そして連休中、待っていた保証書付き冊子が到着しました!
はじめて竪琴を手にされる方に、調弦や、音の出し方、日々のメンテナンス等をまとめました。
これまで口頭でお伝えしていたことが冊子として形になり、嬉しいです。
竪琴と奏者の絆をむすぶ一冊として使って頂ければさいわいです。
楽器を購入して頂いた方に、一台一台の楽器の製造No.を書き入れた保証書としてお届け致します。
連休中はお届けが間に合わなかった方への発送の準備をしていました。
到着までどうぞ楽しみにお待ち下さい。
準備が一段落ついた今日は、久々に海へと行って来ました。
『令和』の訪れと共に激しい雷雨に見舞われた沖縄でしたが
新月の今日は快晴、親子連れが潮干狩りをする姿があちこちに!
竜宮城へ続くような海を歩いて海藻を集めます。
例年より少し肌寒く、海藻が育っていないようでしたが歩くだけで心地よい・・・

他の海藻や砂を洗い流してさっとゆでます。
ツノマタ、と私たちは呼んでいるけれどクビレオゴノリというそうです。

翡翠の様な美しい色!
ごまドレッシングをかけて頂きました。
コリコリと歯触りが良く、全身がさわやかになる感じです。
モーイ(テングサ)も少し生えていたのでモーイ豆腐も作りました。
ツノマタと、ちょっとニンニクを効かすのがうち流です。
連休最後に海でエネルギーをチャージすることが出来ました。
明日からまた制作に励みます

2019年04月17日 15:20



あやはべる9弦の音色≫

あやはべる9弦へお問い合わせいただいた皆様、
ご注文頂いた皆様、ありがとうございます!
お陰様で新月生まれの9台は残り少なくなりました。
気になっていらっしゃる方は、是非お問い合わせ下さい!
さて、『どんな音がするのですか?』
『ペンタトニックってどんな音ですか』
というお問い合わせを多く頂いております。
竪琴奏者の知花洋子先生からすてきな演奏を頂きました。
是非お聴き下さい!
(↓知花先生著のペンタトニックの楽器のための本です!)

ちいさな竪琴と歌う季節の歌 1500円(税込1620円)
ちいさなペンタトニックの竪琴は
『キッズライアー』、『キンダーライアー』と
呼ばれていて、
名前の通り子ども向け・・・と思っている方も多いと思います。
けれども知花先生はこのペンタトニックの楽器の魅力、すばらしさにいち早く気づき
たくさんの方にもっと音を奏でることを楽しんでほしい!
との願いを込めて出版されました。
この音階を使っている音楽はびっくりするほどたくさんあります。
アイルランド民謡、琉球民謡、日本のヨナ抜き音階、わらべうたから
歌謡曲、演歌まで・・・
なぜでしょうか?
秘密はこの音階を構成する音が自然倍音であり、
人がもっとも美しいと思い、安らぐ和音だからです。
はじめて音を奏で、歌が生まれたときの喜びに近い音階といえるかもしれません。
子どもだけに限定するのはもったいない!
丁度すぐれた絵本が子どもだけのためではなく、
おとなにとっても深い感動を与えてくれるように
竪琴を弾き始めた初心者から、
上級者、治療に携わる方にもおすすめします。
音による対話や即興、朗読に合わせたり・・・
大きな竪琴と合わせたり・・・
音とていねいに向かい合う時に適している楽器です。
お届けしてからすぐに弾きたい!という方の為に
☆あやはべる9弦
☆L型調弦器
☆電子チューナー
☆ちいさな竪琴で歌う季節の歌
をセットにしたスターターキットもいくつか準備しております。
着いたその日から竪琴に親しんで頂くことのできるとってもお得なセットです。
価格¥48000(税・送料別途)ですが、
初回限定20台分(残り11台になりました)に限り、
¥45000(税・送料別途)です。
2019年04月10日 12:10


旧3月1日生まれのあやはべる9弦≫

新学期のスタート、新年号発表と新しいピカピカの空気に満ちた
4月5日は旧3月1日。新月でした。

この春の佳き日に、てるる詩の木工房久々の新モデルが誕生しました!

あやはべる 9弦 ペンタトニック
ナチュラル仕上げ
(調弦器、冊子『竪琴の物語』、紙ケース付き)
¥45000(税・送料別途)
”あやはべる”とは琉球の古語で『美しい蝶』を意味する言葉です。
吾が をなり御神の
守られて おわちやむ
やれ、ゑけ
又 弟をなり御神の
又 綾蝶(あやはべる) なりよわちへ
又 奇せ蝶(くせはべる) なりよわちへ
(意)
私のをなり神が
守るために来てくれました。
ヤレ、エケ
妹をなり神が
美しい蝶となって
奇しき蝶となって
『おもろさうし』巻13-965
航海に出る兄弟を、姉妹のをなり神が美しい蝶となって守護してくれる、
という祈りを込めた美しいおもろです。
『あやはべる』という学期の名前はここからいただきました。
ペンタトニック音階の楽器は
『ことのは』だけでしたが、
原点回帰と感謝の気持ちを込めて今回新たなモデルを制作しました。
小さいながらも作りはほぼ大きな竪琴と同じです。
音量もあり、遠鳴りしてきこえます。
音域も9弦と広いです。(ペンタトニックの楽器は7弦がほとんどです)
竪琴の音色を愛する多くの方に、弾いて頂けたらと思います。
感謝の気持ちと、新しいモデルの誕生を祝って今回、
¥39800(税・送料別途)
でお届けしたいと思います。
*数量限定20台です。
お問い合わせを多く頂く調弦の仕方や弾き方、
日々のお手入れ等を冊子にまとめて同封致します。
はじめて竪琴を弾く方にもおすすめ致します。
この春の新月に生まれたあやはべるは9台です。
お問い合わせお待ちしております。

2019年01月26日 19:18





旧12月16日生まれのことのは≫

1月21日は旧12月16日、今年初めての満月でした。
日本では観測できなかったのですが皆既月食だったそうです。
そして夜明け前には金星と木星が美しく輝いていました。
この日、新しいことのはに弦を張りました。

ことのは しいの木・ペンタトニック・9弦
ナチュラル・ポリッシュ仕上げ
2019年1月21日(旧12月16日満月・皆既月食)
¥75000(税別・木製ケース・調弦器込み)
特別支援学校でこども達と向きあっている先生からのご注文でした。
わらび手もまあるく仕上げました。
県外に『まいまいずの井戸』という井戸があるそうです。
(詩人吉増剛造さんの講演会で初めて知りました。)
かたつむりのような螺旋の井戸を下りていくと都会であってもシーンとした空気に包まれます。
昔水を汲む人々は下りるときは皆無口ですが、水をくんで上っていくときには足取りも軽くなり、
自然と誰かがうたを口ずさみ舞がはじまり、喜びをたずさえてくるのだそうです。
沖縄の井(かー)も少し下りたところにあります。
以前獅子頭を制作したとき、魂を込める儀式で(シディガー)という湧き水の出るところに行きました。
シディル、とは羽化する、脱皮する、新しく生まれるという意味です。
獅子が生まれ変わるに当たり、地域の皆さんと共にその井戸で祈りを捧げました。
獅子の姿形は年月と共に変わっても地域を守る魂は生まれ変わりながらずっと続いていることに感動しました。
ことのはの小さな螺旋もそんな井の話を思い浮かべながら彫っています。
高音部4弦は自作のストレート弦です。
弦巻き機も改良中!
弦巻き機を作る機械も製作しながら改良しています。

今日の朝ご飯!
オオタニワタリの新芽を軽く湯がいて、
タラの芽入りのオムレツ。
琉球松で作ったお皿に盛りました。
寒い季節ですが植物はちょっとずつ春に近づいています。
2019年01月18日 21:37






木の歴史≫
ここしばらく製材・木取り・といった地道な仕込み作業が続いています。
倉庫の中の木を引っ張り出し、
適材適所で楽器のどのパーツに使うか決めて製材していきます。
伐採する時期は木が眠りにつく晩秋~冬の初めまで。
水に浸けて樹液を抜いた木を丸太のまま購入し、製材します。
製材するのもどの方向からどの厚みに切るか神経を使います。
一枚一枚年号を記入し、一年間は雨の当たらない軒下で乾燥。
その後倉庫に積み替えて8年~10年乾燥させます。
住宅と工房が一緒なので、10年も寝起きを共に暮らしていることになります。
今回表甲に使う予定の木。
直径70cm以上の大きな桑の木、
綺麗に柾目が通っている最高の木です。
実はこの木、最初丸太から製材した時にあっと驚きました。
中に切られた跡があるのです!!
(写真横に切れ目が入っているところ)
芯に当たって堅くて切れなかったのでしょうか?
若木の頃、何らかの理由で途中まで切られ、その後そのまま傷を包み込むように成長しています。
これだけ切れ目を入れられたにも関わらず、すごい生命力!
まっすぐで目が詰まっていて、こんなに大きく成長しているのです。
今回、楽器のために木取りしながらもほとんど狂いが生じませんでした。
ものを言わない木ですが、生き様を通して語りかけてくるものがあり、感動しました。
中にはこんな木もあります。
赤いまるで囲んであるところに鉄砲の弾が入っています。
弾の材料である鉛は比較的柔らかい金属なので刃物を痛めずに済みました。
戦争の時なのか、それともイノシシ猟の物なのか今となってはわかりません。
小さな種から芽生えて、光を求め大きく育ち、鳥や虫や小動物と共に暮らし、風雨に打たれ・・・
木は長い年月の中で、人と喜びも悲しみも共にしている、材となっても生命を持っている。
外から見てもわからない、木の内包している木目や美しい杢、
そしてこんなことに出会うとそんなことを感じるのです。
2019年01月14日 09:49



ムーチーの日に≫

今日はムーチー。
月桃の葉で餅を包んで蒸し、こどものいる家庭では
その子の年の数だけ軒につるして健康を願います。
その子の年の数だけ軒につるして健康を願います。
写真は以前earth photographer西美都さんに撮影して頂いた一枚。
場所はムーチー伝説のある首里金城町の大アカギです。
今は木の保護の為にこの場所は立ち入り禁止となっており、奇跡の一枚となりました。
木に竪琴が抱かれている、とても大好きで大切な写真です。
沖縄の冬の寒さは4回来ると言われています。
1、冬至寒さ(トウンジービーサー)冬至の頃の寒さ。仏壇にジューシー(炊き込みご飯)をお供えします。
2、ムーチー寒さ(ムーチービーサー)ムーチー(餅)の頃の寒さ。前述のムーチーをお供えします。
3、戻り寒さ(ムドウイビーサー)寒さが和らいだかな?と思ったら寒くなる。寒の戻り。
4、別れ寒さ(ワカリビーサー)最後に来る寒さ。過ぎ去ったあとに『あの寒さが最後だったかな・・・』と冬に別れを惜しむ寒さ。
不思議と昔の暦は良く当たり、それまで温かくてもムーチーになったら
急に寒くなったりもするのですが今年は温かい一日でした。
お陰で仕事も快適に進みました。
仕込みの時期は種を蒔いているような感じで見た目にはあまり進捗がわかりません。
でもとても大切な時間なのです。
『たいていの生き物の始まりは、光のない場所で起こる。
ブドウは地面に根を張り、子鹿は雌鹿の子宮の中に形をとる』
ナンシー・ホールダー

ご近所からいただいたムーチー。三時休みにおいしく頂きました。
ありがとうございます!
2019年01月07日 22:37

昨年中は大変お世話になりありがとうございます。

以前より研究していた弦がやっと納得いくものが作れるようになった為、

旧12月1日のことのは≫
昨年中は大変お世話になりありがとうございます。
2019年もどうぞてるる詩の木工房をよろしくお願い致します。
時々『なんと読むのですか?』と質問を頂きます。
改めてお伝えしますと『てるるうたのきこうぼう』です。
工房を作った2002年のクリスマスに初めて竪琴の音色に出会い、
沖縄の木で楽器を作りたい!と思い立ってから17年となります。
当初は注文家具工房としてのスタートでしたが
木工の原点がギター製作所だったこともあり、少しずつ竪琴の試作を繰り返し、
2010年に楽器部門に『てるる詩の木工房』と名前を付けました。
自分で作った楽器に責任を持ちたいと思い、名前の一部を入れました。
そして『木がうたをうたってほしい』という願いを込めています。
最初であった楽器はドイツのゲルトナー製の楽器でした。
制作を始める際、奏者の平岡祐子さんから『深い泉から水をくんで下さい。』という言葉を頂きました。
日本では琴と言葉に深いつながりがあること、沖縄でも弓の音で魔物を払う風習があること。
遠い国の楽器と思っていた竪琴がいろいろな地域で弦楽器の祖、として使われていること。
深い水脈が世界中を巡ってつながっていることを実感できたとき、
はじめて自分の心の中から湧き出る楽器として作ることができました。
『ことのは』は工房で一番はじめに生まれた竪琴です。
琴がことば=言の葉とつながりがあり、音によって邪を払ったり整えたりする、
という伝承へのオマージュから名付けました。
一つの木から彫りだして作られており、ピュアな音がします。
以前より研究していた弦がやっと納得いくものが作れるようになった為、
年が明けて初めての新月そして部分日食だった1月6日、
弦の張り替えを依頼されていたことのはの弦を新しくしました。
今はまだ高音部5弦のみですが、今後制作する楽器や張り替えの際には
自作の弦で対応が出来ます!
音もクリアでよい響きになりました!
今回大活躍の弦製作器!
これからさらに改良を加えます。
いろいろな方のご協力により実現致しました。
この場を借りて感謝の意を表したいと思います。
本当に小さな一歩かもしれませんが私たちにとっては大きな一歩となりました。
今年は『猪っとずつ猛進』(ちょっとずつ・猛進)で頑張ります!
どうぞよろしくお願い致します。
2018年12月19日 17:14






12月14日生まれのてるる39弦普及版≫
温かな沖縄も冬の訪れを感じます。
双子座流星群の最大日だったこの日、
制作していた新しい楽器に弦を張りました。

てるる39弦普及版
2018-12-伊集-う
沖縄県産伊集材・スチール弦・セミアーチトップ
ナチュラル仕上げ
通常価格¥350000(税別・木製ケース・調弦器込み)
のところ→¥300000
※売約済みです
なぜかというと、この楽器は制作途中フレーム本体に少し補修があります。(内側に)
また甲の材料は柾目が通っていますが節が多少あります。
音には問題ありませんし壊れやすい訳ではありません。
表甲・裏甲共に伊集材を使用しています。
リボン杢が現れ美しい木です。
この一台のみですので気になった方はご連絡下さい。

実はこの楽器、途中で難に気付き制作をストップしていました。
けれども今年のテーマが『再生』だなあ・・・と思い、一念発起して再生しました。
ケルトのアーサー王伝説の中に名剣エクスカリバーを再生するお話があります。
アーサー王は父から譲り受けたエクスカリバーを折ってしまうのですが
自ら鍛冶を習い剣をを打ち直して再生させます。
作るとはただ一度作るだけではなく、『再生』に意味がある、何度でも『再生』できる・・・
そんなお話を聞いてとても希望を頂きました。
例年になく降り続いていた長い雨がやみ、この日は清々しい朝でした!
幸運の印とされる黄色いテントウムシ発見!(見つけたあなたにも幸運が訪れるかも!?)
また、2019年度制作分の竪琴ご予約も承っております。
年内でご予約の方には増税後も現行価格で対応致します。
2018年12月05日 18:08
 明け方、まだ日の昇らぬ暗い時間。
明け方、まだ日の昇らぬ暗い時間。






ビーナス≫

東の空に輝く金星(ビーナス)。
この日は新月前の細い月と並んで本当に美しかった。
太陽が昇ると消えてしまうわずかな時間だけれど
対話しているようでここ2ヶ月位ずっと朝が楽しみなのです。

朝日の当たる場所にナンクルミ-(植えていないのに勝手に生えてきた)したランタナ。



まるで金星を映しているかのように毎日表情が変わります。
きれいな五紡星が現れたのにはびっくり!
金星は地球に近づいたり離れたりしながら五弁の花びらのような美しい軌道を描いているそうです。
遠い星とこの小さな花が対応しているのですね。
2019年度の竪琴ご予約受付中です。
年内ご予約の方は増税時にも今年の税額で対応致します。
ご注文頂いた方々、真にありがとうございます!
今月は仕込み月間、畑で言えば耕したり畝を作ったり種を蒔いたり、といった時間です。
まだ完成していない楽器に思いを馳せながら原木を製材して
部材の木取りを進めています。
10年以上乾燥させ、楽器になる時を待っていた木たちが目を覚まし始めています。
ご注文、お待ちしております!
2018年11月28日 09:42



2019年度・竪琴予約について≫
あと一月で年の瀬ですね。
来年度制作予定の楽器を現在仕込み中です。
主にてるる39弦(上製・普及版)を製材し、パーツごとに制作を進めています。
樹種は桑・伊集・しいの木。
ことのは9弦も数台準備中。
あやはべる32弦は39弦完成後に取りかかる予定です。
制作期間は普及版が3ヶ月~半年、
上製が半年~一年位かかります。
ことのはは1ヶ月~2ヶ月です。
もし、ご購入をご検討されている方がいらっしゃいましたら・・・
ぜひ今年のうちにご予約されることをおすすめ致します。
なぜなら・・・
来年度は消費税アップの予定もあり、様々な部材の値上がりが予想されます。
今回ご注文いただいた方には現行のお値段でお渡しできます。
ご注文の多いモデルから制作していきますので
今ご注文頂くと最速で制作できます。
見込み制作で作っていても作っている間にご注文が入ることが多く、
完成頃にはほとんど行き先が決まってしまいます。
樹種やモデルによって価格や納期がそれぞれ違います。
個々の楽器についてはメール・お電話・FAX・お手紙等でお問い合わせ下さい。
(メールは時々迷惑メールに振り分けられてしまう場合があります。
もしもこちらからの返信が無い場合は一度お電話下さい。)
新しい年にどんな楽器が生まれてくるのか、そしてどんな方に弾いていただけるのか、
仕込みをしながらまだ見ぬ出会いを楽しみにしています。
お問い合わせ、ご注文、お待ちしております。
↑甲接着のための鉋がけ。
機械だけではぴったりと隙間無く接着は難しい。
手作業で、ほんの少し真ん中がすくように鉋を当てるとぴたっとくっつきます。
↑膠(にかわ)で接着したところ。
均等に玉のように余分な膠が出てきたら綺麗に接着できた証です。
2018年11月21日 09:37





蛸取り物語≫
去る日曜日、念願の蛸取りに出かけました。
もう2年ぶりぐらいです。
貝をいくつか付けたひも(ンヌジベントー:タコの弁当)と呼ばれる道具をカーボーイのように回して海に投げ、
くっついてきたタコを手で捕まえる伝統的なスタイル。
これが楽しいのです!
いつでも取れるわけではなくて丁度いい時期と潮の満ち引きのタイミングがあります。
時期になると20~30人ぐらいの人が海で捕っているのを見かけるときも。
タマン釣りの餌用にする人も多く、すっかり秋の風物詩となっています。
雨が降ってもタコが沖に行ってしまうし、晴れすぎても用心深くなるので不向き。
暦と仕事の進捗とにらめっこしながら今年最後のチャンスかも!と出かけました。
この海にチャポンと投げて引くと、どこからともなくタコが現れて貝にしがみつきます。
あっ!と思って手が止まると気づかれて逃げたり隠れたり。
どんな種類でどんな大きさの貝を使うかでも捕れ方が違うので皆それぞれ工夫しています。
(最初釣具屋で買った仕掛けを使ってたら見知らぬおじさんに『あんたこれ買ったやつでしょ。これじゃあ釣れないよ』と言われた・・・)
さらにはタコにも貝に好みに流行があるらしく、毎年ブームが違うらしい。
エギに使うかぎ針だとくっついた時点で捕獲できますが
このやり取りが楽しいので取れる数は少ないけれどこの方法が一番!
本日の釣果は輝幸6匹、のり子1匹、次男0匹でした。
ちなみにこんなのが捕れます。(かわいいでしょ!?)
早速塩でもんでぬめりを取り、ゆでました。
お昼はたこ焼きにして、夜は味噌バター炒めにして最高でした!
畑もゴーヤー、なすの夏野菜から
タマネギ、ジャガイモ、ニンニクといった秋植えの野菜に。
雑草だらけだった畑も草を取り、耕し、植え付けをして新芽が育ってきています。
2018年11月14日 20:43





ドイツ研修記(エピローグ)≫
ドイツで割れてしまった箇所を修理し、再生したアルトライアー。
イースターには『再生・復活』の意味があったのでした。
今回はニーダー氏が送ってくれた弦を張りました。
低音部2弦は自分で作った弦を張っています。
現在は弦を自分の工房で製作するべく、日々研究中です。
あれからよく虹に出会うような気がします。。
愛犬ブランカと散歩中も・・・
工房の機械にも・・・
虫にも虹が現れました!
旅の終わりは新しい旅の始まり。
弦を作る旅はまだまだ続きます。
2018年11月13日 19:21

ドイツ研修記⑦≫
とうとうお別れの日がやってきました。
長いドイツの旅も終わりです。
帰る日の朝、ザーレム工房の前で写真を撮りました。
貴重なイースター休みをさいて、惜しみなくご自身の技術や研究を教えて下さったニーダー氏、
いつも目にも美しいお食事を用意してくれて明るくもてなして下さった奥様のエスタさん。
心よりの感謝を捧げたいと思います。
遠いドイツで今日もお元気でライアを製作し、散歩に出かけ、薬草スープを作っていらっしゃることを思うだけで胸がいっぱいになります。
またきっかけを下さったスザンネ先生、木についていろいろ教えて下さった息子さん、
格安料金で、そして毎日大笑いして楽しく過ごせた宿屋のシャーラー夫妻。
通訳をして頂いたKさんとパートナーのSさん、
そしてペロルの井出芳弘さん。
弦を製作して下さったヘレンさんを始めザーレム工房のスタッフの皆さん。
ドイツで出会ったたくさんの親切な方々。またこのブログを読んで楽しみにして下さる方を始め、
いつもてるる詩の木工房の竪琴を弾いて、応援して下さっている方々。
皆様に深く感謝致します。
この旅で学んだこと、感動したことをいつの日か
楽器を通してお伝え出来たらと思っています。
虹の色は同じ太陽の光。

いつもてるる詩の木工房の竪琴を弾いて、応援して下さっている方々。
皆様に深く感謝致します。
この旅で学んだこと、感動したことをいつの日か
楽器を通してお伝え出来たらと思っています。
虹の色は同じ太陽の光。
隣り合った色が違うからこそ虹は美しい。
それぞれが自分の色を大切にして、他の色に染まる必要はないのです。
それぞれが自分の色を大切にして、他の色に染まる必要はないのです。
七つの音それぞれが違うから美しい歌が生まれてくるように。
そして心の中の太陽を輝かせたら
もしも涙に出会うことがあってもそこにきっと虹が現れる。
遠いドイツで出会ったのは
『自分の心の中の太陽(ティダ)』でした。
『自分の心の中の太陽(ティダ)』でした。
(帰りの飛行機。ハートに見守られて沖縄に帰ってきました!)
続きを読む ドイツ研修記エピローグへ
2018年11月12日 20:32











ドイツ研修記⑥≫
異変に気づいたのはしばらくしてからでした。
チューニングが狂いだし、
まさか・・・と思いサドル部分を見ると本体との接合部分がはがれてしまっていたのです。
言葉にならない位ショックでした。
弦を改善することで音が良くなればきっと弾いて頂いている皆さんに喜んでもらえる
という一心でドイツに来たのに・・・
ニーダー氏もヘレンさんもあんなに一生懸命弦を作ってくれたのに・・・
応援して下さっている皆さんの顔が思い浮かび、
なんとも情けない気持ちで眠ることもできませんでした。
眠れない夜を過ごし、明け方は心模様を映すように雨が降っていました。
雨がやみ朝日が昇ってきました。
その時なんと!虹が出たのです!
『大丈夫!』また元気が出てきました。
今後の楽器の改善策も決まりました。
朝食前ニーダー氏に楽器が壊れたこと、修理、改善が必要なことを伝えると
彼はうなだれて高良の肩に手を置き『ショック・・・』。
この冬ドイツはとても乾燥していて少しずつ楽器を慣らさなくてはいけなかった、と言っていました。
そして御自身の失敗談を話してくれました。
この日ニーダー氏はたくさんの古い楽器を見せてくれました。
ゲルトナーの初期の楽器にはライアーを開発するにあたっての失敗や苦労の跡がつぶさに見て取れました。
古代の楽器を復元した楽器、彼が考案した楽器、様々な楽器を手にとって音を感じました。
それぞれの楽器でスケールデザインが違い、
ニーダー氏が言うように『弦は楽器にとって神経であり血管』。
それぞれの楽器に合わせて調整を繰り返すことが必要なのです。
もしもハプニングがなければこういった時間は無かったでしょう。
私たちは多くの学びの時を得ました。
午後はニーダー氏が車で20分位のところにあるハイリゲンベルグ城に案内してくれました。
入り口にあった菩提樹の古木。900年の樹齢なのだそうです。
このお城はいつでも観光できるのではなく、申し込みが必要です。
また何組かそろってからガイドさんが案内してくれます。
入場料はお城の維持管理に使われているそうです。
なぜかフランスの国旗が掲げてあるのでニーダー氏に聞いたところ、
『今日の一行はフランスからなので。スペインの人が来るときはスペインの国旗になる』と言って笑っていました。
お城の台所。大きなオーブンやジャガイモの皮むき器、ソーセージミンチ、アイスクリーム製造器までありました。
お城のあちこちで見かける金具はケルト模様特有の渦巻きや端っこが動物になった模様。
ニーダー氏の話では元々この土地はケルト民族が支配していた場所で、
ここより南に行こうとしたがアルプスに遮られて行くことができなかったそうです。
大広間のピアノは竪琴型でした!
お城を出てボーデン湖を遠くに臨みながら歩きました。
ザーレム地方で最初工房を立ち上げそれからここに移ってきたこと。
奥様がスイス出身なのでスイスが見えるこの地を選んだことなど話してくれました。
菩提樹の並木道を歩いているとニーダー氏が
『あなた方を写真にとってもいいですか?』と彼の携帯で写しました。
弦作りの師匠であるニーダー氏と。
長かった一日の夕方。
奥様も一緒にお茶を飲みながら彼は英語でいろいろな話をしてくれました。
(時々『う~ん!!英語ではなんて言ったらいいんだ・・・』と頭を抱えながら)
私たちは朝見た虹の話をしました。
沖縄では『カタブイ』といってある場所では雨が降って、ある場所では晴れていることがある。
でも雨のあとには虹が出てくること。
そしてあきらめずに弦作りにチャレンジすることも。
その時窓の外に雪が降ってきました。
雪はやがて雨に変わり、
雨が上がると再び大きな虹が現れたのです!
一日に2回も虹を見たのは初めてです。
4人で大きな虹を眺めました。
もうすぐお別れの日が近づいてきています。
続く ドイツ研修記⑦へ
2018年11月11日 11:03







旧10月1日生まれのてるる41弦≫
11月8日は旧10月1日、新月でした。
この日新しく製作した2台の楽器に弦を張りました。
長らくお待ち頂いたお客様には本当にありがとうございます。
山に生えている木を伐るのに一年で最もふさわしいとされている特別な日。
ヨーロッパにも、日本やオーストラリアにも、
『この日に切った木や竹は狂いや割れ、虫が少ない』という伝承があり、
ストラディバリウスの楽器も『新月の木』で作られていているそうです。
私たちも材木を買い付けするのはこの時期の木です。
てるる41弦(クラシックモデル) 桑 上製
2018年11月8日 製作
¥730,000(木製ケース・調弦器付・税別)
※売約済
以前製作していた大型41弦の限定復刻版です。
てるる41弦 桑 上製
2018年11月8日 製作
¥680,000(木製ケース・調弦器付・税別)
※売約済
毎年この頃に完成する竪琴は深い色味の仕上がりとなります。
同じように漆を使っても空気中の温度や水分で仕上がりが変わってきます。
この日は朝から晴天、楽器の誕生を祝うように工房の周りでたくさんの花が咲きました。
桑で製作した楽器。
この日のおやつはたわわに実った桑の実!
楽器を作るのは山の中でこのように光を求めて育った木。
伐採し、池に浸けて樹脂を抜き、製材して8年以上工房で共に過ごした木。
一年以上かけて楽器の姿になった木に思いを馳せました。

弦を張る作業は夜遅くまで続きます。
月明かりのない新月の夜、星がたくさん輝いていました。

(ドイツ留学中の娘から送られてきた写真。紅葉して散りゆくメイプルの葉がまるで星が舞っているよう!!)