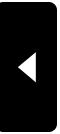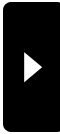2018年11月07日 22:24

明くる日。
朝ごはんは奥様のエスタさん特製のスープ(お粥?)です。
オートミールや海藻、スパイスが効いていて野草がたっぷり入っています。
昨日の散歩の時、別のルートに行ったエスタさんが摘んでくれた
特別な野草、ハーブなのだそうです。
聖書を読みお祈りをしている間、犬のニラちゃんが『ウー』と
何かつぶやいています。一緒にお祈りしているのかな?
その後食卓にいる全員で手をつないで輪になり
『ゲーゼイグ ネッテ マール ツアイト』(祝福された食事の時間)
と言ってからいただきました。
とても元気のでる不思議なスープでした!

工房に入ると木工機械の音、木の香り。
住宅と工房が一緒で毎日木と向きあっている私達にとって
日常に出会えてドイツを訪れて一番リラックスできました。
竪琴についてや、木や金属について、製作者としての話を一日中たくさんしました。
ライアー工房の話になり、いくつかの工房の話の後、
ドイツ研修記⑤≫

(泊まったお部屋の窓から。飛行機雲が縦横無尽に走っていてヨーロッパの空は人が行き交うのを感じました。)
朝ごはんは奥様のエスタさん特製のスープ(お粥?)です。
オートミールや海藻、スパイスが効いていて野草がたっぷり入っています。
昨日の散歩の時、別のルートに行ったエスタさんが摘んでくれた
特別な野草、ハーブなのだそうです。
聖書を読みお祈りをしている間、犬のニラちゃんが『ウー』と
何かつぶやいています。一緒にお祈りしているのかな?
その後食卓にいる全員で手をつないで輪になり
『ゲーゼイグ ネッテ マール ツアイト』(祝福された食事の時間)
と言ってからいただきました。
とても元気のでる不思議なスープでした!

(スペシャルハーブ、といっていたのはなんと行者ニンニクでした。)
工房に入ると木工機械の音、木の香り。
住宅と工房が一緒で毎日木と向きあっている私達にとって
日常に出会えてドイツを訪れて一番リラックスできました。
竪琴についてや、木や金属について、製作者としての話を一日中たくさんしました。
ライアー工房の話になり、いくつかの工房の話の後、
『私は12の工房を知っていますがあなたは13番目の工房です。』と言ってくれました。
実際の作業の際には簡単な英語や持っていったスケッチブックに絵を描いたり
ドイツ語で書いてもらったりしながら何とか理解し合えたのですが
抽象的な事柄についてはお手上げ。
ペロルの井出さんには彼が帰るまで通訳をして頂いて本当にお世話になりました。
お陰でニーダー氏と心を通わせることが出来、語学の大事さを痛感しました。
いよいよ弦を作る研修が始まりました。
ソプラノライアーでは弦の太さを指定することで対応出来たのですが
アルトライアーでは自分の楽器に合わせた弦を作る必要があります。
そこで自作の弦巻き機械を作り、様々な金属のワイヤーを探して
巻き弦を作っていたところ、その弦を見たニーダー氏が
『この楽器についてはプロフェッショナルの仕事だけど、
実際の作業の際には簡単な英語や持っていったスケッチブックに絵を描いたり
ドイツ語で書いてもらったりしながら何とか理解し合えたのですが
抽象的な事柄についてはお手上げ。
ペロルの井出さんには彼が帰るまで通訳をして頂いて本当にお世話になりました。
お陰でニーダー氏と心を通わせることが出来、語学の大事さを痛感しました。
いよいよ弦を作る研修が始まりました。
ソプラノライアーでは弦の太さを指定することで対応出来たのですが
アルトライアーでは自分の楽器に合わせた弦を作る必要があります。
そこで自作の弦巻き機械を作り、様々な金属のワイヤーを探して
巻き弦を作っていたところ、その弦を見たニーダー氏が
『この楽器についてはプロフェッショナルの仕事だけど、
弦については私は40年間研究しているので工房に来たら教えてあげるよ』
と言って下さったのです。
彼はゲルトナー工房から独立後、
あちこちの弦製作所に教えを乞いに行ったそうです。
親切に教えてくれた所もあれば冷たく断わられた所もあり、
さらに自分で研究をして現在も研究中とのこと。
『弦を作るのは大変でお金もかかりますがとても楽しいことですよね!』
と言っていました。
いくつかの工房に教えたのですが実際に製作している工房は少ないそうです。
今回は私達のアルトライアーを沖縄から持参しました。
弦を製作しているのは工房のヘレンさん。
彼女は事務として入ったのですが手先がとても器用ですぐに
弦を作ることになったそうです。
ニーダー氏が計算を行い、彼女が弦を巻いて張替えていきます。
作業は3日に及びました。
とうとう完成した時、ニーダー氏はニッコリ笑い、
『今日は部屋に持ち帰って弾いて下さい。ひょっとしたら一晩中眠れないかもしれないですね。』
と言って下さったのです。
彼はゲルトナー工房から独立後、
あちこちの弦製作所に教えを乞いに行ったそうです。
親切に教えてくれた所もあれば冷たく断わられた所もあり、
さらに自分で研究をして現在も研究中とのこと。
『弦を作るのは大変でお金もかかりますがとても楽しいことですよね!』
と言っていました。
いくつかの工房に教えたのですが実際に製作している工房は少ないそうです。
今回は私達のアルトライアーを沖縄から持参しました。
弦を製作しているのは工房のヘレンさん。
彼女は事務として入ったのですが手先がとても器用ですぐに
弦を作ることになったそうです。
ニーダー氏が計算を行い、彼女が弦を巻いて張替えていきます。
作業は3日に及びました。
とうとう完成した時、ニーダー氏はニッコリ笑い、
『今日は部屋に持ち帰って弾いて下さい。ひょっとしたら一晩中眠れないかもしれないですね。』
2018年11月02日 21:30








ドイツ研修記④≫
さて、全くドイツ語を話すことの出来ない私たち。
ホルスト・ニーダー氏はドイツ語のほかに英語も少し使われていましたが、奥様はドイツ語のみ。
タブレットの翻訳機能ではとうてい会話に対応出来ず、
通訳のkさんが帰ってしまわれた後はどうやってコミュニケーションを取っていいやら・・・
でも案内して頂いたお部屋にこんなすてきな奥様手作りのカードが!
『Herzlich willkommen』(ようこそ、温かくお迎えします、という意)
そして昼間ニーダー氏が言っていた言葉がよみがえってきました。
『あなたの心のなかの太陽で聴いて下さい。』
まずはゆっくりと眠ろう♪
それまで時差でなかなか寝付けなかったり、明け方3時頃目が覚めてしまったりでしたが
温かな気持ちに包まれてぐっすりと眠ったのでした。
次の日の朝からは幸運なことに福岡県でザーレム工房ライアーを販売するお店、
ペロルのオーナー井出芳弘さんが一緒でした。
いろいろと細かいニュアンスまで通訳して頂いて本当にありがたかったです。
この時ほど言葉の勉強をしていなかったことを残念に思ったことは無かったです。
一日の仕事が終わると散歩に出かけます。
遠くにアルプス山脈が見える草原をどこまでも歩きます。
スプルースの森。
風が吹き抜けると葉の擦れ合う音がします。
大きなブナの木。
ふきのとうもありました。
でもドイツ語では『ペストの薬』という意味で食べないとか・・・
時期にはキノコも生えるそうですがチェルノブイリ事故以来食べないのだそうです。
村の小さな教会。中に入らせて頂くと竜を退治する聖ゲオルグの像がまつられていました。
ニーダー氏の工房のほかにこの村にあるのは牛舎、犬を預かるホテル、退役軍人の家、築250年の古い空き屋、
あと数軒・・・
とても静かなところです。
教会の入り口で咲いていたスノードロップ。
長い散歩を終えて帰ってきました。
ニーダー氏の工房です。
一階にはホールに改築中とのことでした。
続く ドイツ研修記⑤へ
2018年10月26日 18:53



ドイツ研修記③≫
ミュンヘンからザーレム工房のあるスイス近くの町を目指します。
電車を乗り継ぎ4時間余り。
そこから通訳のKさんの車でさらに進みます。
風景がどんどん変わってきます。
岩山が多い地形から牧草地、ブドウ畑やリンゴ畑、広々とした農村へ。
途中スイスアルプス山脈を見渡すことの出来る丘へやってきました。
広大で澄み切った空気。
ボーデン湖も見えます。
この向こうはスイス・フランス・オーストリア。
普段は曇って山が見えないことが多く、
こんなに晴れた日は珍しいとのことでした。
スザンネ先生の息子さんに「イエローチェリー」と教えてもらった黄桜の大木を見つけました!
知っている木があるとなんだか顔見知りに会ったようで嬉しい。
ザーレム工房に向かう途中で食事をしたレストランの看板。
ちょっと緊張気味でしたが
「大丈夫、がんばって!」と天使が言ってくれてるようでした。
いよいよ工房へと向かいます。
続く ドイツ研修記④へ
2018年10月25日 09:32

















ドイツ研修記②≫
今回のドイツ旅行はスザンネ先生のレッスンとザーレム工房での弦製作研修が目的だったので
観光は予定していませんでした。
けれど一日だけは通訳をして頂いたドイツ在住10年のKさんの案内でミュンヘン市内を観光しました。
電車に乗るのも(切符を買うのも)ドキドキ・・・
マリエンプラッツ駅で降りた私たちを迎えてくれたのは大きな市庁舎の建物でした。
見上げる高い塔には有名なからくり時計が。
ちょうど人形達が回っていていました。
オペラハウスの横を通り、バイエルン王国の居城レジデンツ宮殿の宝物殿へ。
もうすでに扉の木彫でワクワクしています。
中はグリム童話のお城の世界。
写真撮影OKだったので何枚も撮りました。

当時はエメラルドやルビーといった宝石も非加熱、無着色。真珠も天然真珠。
見事な黄金の彫金や石止め技術には息をのみます。

ちょっとだけ王様の気分。失礼!
これは琉球漆器の螺鈿に使われる夜光貝。
どのような旅を経てドイツに来たのでしょうか。
中には教会がありました。
第2次世界大戦で破壊された煉瓦を市民が拾い集め、足りない部分を補って戦後すぐに復興されたそうです。
楽器を集めた部屋もありました!
すっかり絢爛豪華な宮殿に圧倒され目クワッチィー(目のごちそう=眼福の意)
のあとはおいしい料理を頂きました。
ミュンヘンの白ビール醸造所の直営レストラン。
冬の間地面の中でたくさんのミネラル・ビタミンをためて伸びるため、
春の時期にしか食べることの出来ないシュパーゲル(白アスパラ)。
普通の緑のアスパラとは区別されています。
専用の鍋で立てた状態で20分くらいゆでるのだそうです。
指ぐらい太くてとても味が濃く、おいしかった!この滞在で2回食べました。
イースター(復活祭)は太陽が日一日と温かさを増し、
復活と再生の祭りでもあります。
(街角で再生を意味するかえるモチーフを発見。)
2018年10月24日 09:30



ドイツ研修記①≫
今年3月末~4月初めにかけてドイツに研修旅行に行って参りました。
竪琴奏者のスザンネ・ハインツ先生が沖縄にいらしたことがきっかけで
ザーレム工房のホルスト・ニーダー氏からのお招きを受け、弦作りの研修の旅です。
古代の楽器であった竪琴を再び現代の楽器として生み出したエドモンド・プラハトとローター・ゲルトナー。
そのゲルトナー工房から独立し、彼自身の工夫を随所に凝らしてライアーを制作するホルスト・ニーダー氏。
すぐにお返事を出し、忙しい彼がイースター休みであれば時間がとれるということで一年近く前から計画を立て、実現しました。
ドイツ滞在最初はスザンネ先生の住むミュンヘンへ。
レッスンの合間にスザンネ先生の息子さんが川の畔の森にハイキングに連れて行ってくれました。
彼は庭師(ガーデナー)。
とても植物に詳しく、木が大好きな私たちにはとても楽しかったです。
シラカバ、オーク、トネリコ、スプルース、カスターニャ、川柳等々・・・一つ一つ木の名前を聞きながらドイツの自然を感じました。
長い冬が過ぎ春が目前の季節、散歩道にはたくさんの花が咲き始めていました。
ちなみにドイツでは職業名も名字になっていて
ゲルトナーは(ガーデナー=庭師)、シュタイナーは(シュタイン=石)で石工の意味だそうです。
続く ドイツ研修記②へ
2018年10月23日 16:27

2台のてるる41弦が漆塗りに入っています。

てるる41弦制作≫
2台のてるる41弦が漆塗りに入っています。
全ての工程を終え、仕上げに入った楽器達はとてもうれしそう。\(^0^)/
わーい!と笑っているように見えます。
制作中は型にはめたり、金具で押さえたり、削ったり。
だんだんと無駄をそぎ落とし、型から放れて自由になっていく楽器達。
この2台は桑の木製。
削りながらも心地よい音が工房に響きます。
完成までもう少しです。
2018年08月21日 13:47




オリーブの実がなった!≫
沖縄は今週木曜日23日からお盆です。
帰ってくるご先祖様達が足下につまずかないように、
とお墓や屋敷周りの掃除をします。
草刈りが終わった夕べ、涼しい風に月を見上げると・・・
あれっ!梢にオリーブの実を発見!!!
油を絞るまではいきませんが、20個ぐらい実をつけていました!
この木は7年前に亡くなった義母が本当に小さな枝を挿し木して育ててくれた木です。
木は大きくなったものの、実をつけたのは初めてです!
義母の植えた木はほかにもあって、シークワーサー、柿、
草刈りをして初めて実に気づくものばかり。
木は約束を忘れていないよ。
いつもどこかで見守ってくれている、そんな気がして嬉しくなりました。
そして心の庭の中にも気づかずに成長して熟しているものがあるかも!と思いました。
時々は草刈りをして風通しを良くして自分の宝物を発見してみよう。
畑では今年初めて植えてみた黒ごまが成長中!
つりがねの様な花を飛び回るミツバチ、それをねらう花グモ、ゾロゾロ集うカメムシ、
いろいろな生き物が共生しています。
おいしいごまを食べる日を夢見て、たくさんのさやを眺めては皮算用を楽しんでおります。
2018年08月19日 12:51








最初に握手するところ≫
楽器が塗装に入り、空っぽになった机の上で
なにやら黄色い木くずが・・・
そうです!
答えは楽器ケースの取っ手を作っているのでした。
今回はハゼの木を使っています。
ハゼの木で有名なのは木蝋(モクロウ)が取れること。
燃やしても煙のでない和ろうそくの原料になったり、
お相撲さんの鬢付け油の原料になったりします。(化学製品のヘアワックスでは髪型をキープできないそうです)
木部にもワックス分がありなめらかで丈夫な材です。
その丈夫さとしなりを利用して
和弓は竹でハゼの木を挟み込むようにして作られています。
大伴家持の和歌のなかにも『天のはじ弓』(天から授かった神聖なハゼの弓)
という言葉が出てきます。
弓と矢を持ち神代に天皇の伴をしていたのが大伴一族で、
その名を汚したり一族を絶やしてはいけないという歌です。
古来弓は敵を射る武器としてよりも、
弓から出る音に力が宿り、場を清めることができるとされてきました。
ケルトの神話の中にも竪琴の音で眠らせることで戦いを止めた話がでてきます。
音には不思議な力が宿っているのです。
小刀で削り、形を整え・・・
磨きをかけて完成です。
ハゼの木のワックス分でつやつやに仕上がりました。
ケースは楽器の帰る大切なお家。
温度や湿度、衝撃から楽器を守ってくれます。
お気に入りのシルクの布で赤ちゃんを包むように楽器を包み、
ケースに入れることをお勧めしています。
特に暑い夏場は高温になる車の中にケースを置かずに室内に移動させる、
陰の涼しいところに駐車することをご注意下さい。
建築のデザインも、ドアの取っ手のデザインから
家一軒の全ての設計が始まるそうです。
ケースの取っ手もある意味楽器よりも先に
奏者の方と出会い握手する大切な場所なのです。
2018年08月18日 18:18
旧7月1日生まれのてるる39弦≫
8月11日は旧7月1日、新月でした。



この日新しく出来上がった伊集の木のてるる39弦に弦を張りました。
てるる39弦 2018年-8月-伊集-1
本体:沖縄県産 伊集材
表甲:北米産 スプルース材
¥568,000(税別・木製ケース付)
柾目の通ったリボン杢のとても美しい材でした。
伊集の木は低音が柔らかく優しい音色です。
完成まで長い時間待って下さって本当に感謝です。
さて、毎年次男の作る梅干しが干し上がりました。
今年はいくつもの台風に翻弄され、なかなかチャンスが現れず・・・
でも台風が空気を吹き飛ばしてくれたのか
澄み切った空気の中で三日三晩の土用干しが出来ました。
立秋ぎりぎりのタイミング、
真夏の太陽のエネルギーをぎゅっと濃縮したような梅干しとなりました。
こちらも完成です。
2018年08月13日 14:31






江洲獅子舞≫
私たちは楽器に弦を張り、楽器が生まれてくる日を
新月か満月に合わせるようにしています。
ことのはに弦を張ったこの日、
もう一つ大切な出来事がありました。
去年から製作を進めてきたうるま市江洲の獅子頭に魂を入れる日だったのです。
代々獅子は新調されると前の獅子に宿っていた魂を一旦抜き、
新しい獅子に移し替えるのです。
獅子の姿形は時代と共に変わっても
魂は何百年もその地域を守っているのです。
デイゴ材を彫刻し・・・
獅子のたてがみとしっぽの為に馬の毛をなめして・・・
漆を塗り重ね・・・
最後は地元の皆さんと共に一年がかりで獅子の毛をつけました。
(これはやった人にしか分からない、地道で大変な作業なのです。
作業をされた皆様本当にお疲れ様でした!)
でも『鳥肌が立つ』という言葉があるように獅子の感情や息づかいはこの毛で表現される大切な作業なのです!
魂を入れる前の獅子。
毛やしっぽが完成し、胴体と結びつけると生きているようです!
そして佳き日に魂を込める儀式が地域の方々によって行われました。
これまで製作に携わってきた日々を思い浮かべながら、
この獅子が地域の獅子として新しく命をいただいたて本当に嬉しかったです。
地域の産川(ウブガー)で祈りを捧げている際には美しい蝶が飛んできてじっと見守ってくれました。
無事に魂入れが出来たことを報告して祈っているときにも同じ蝶が飛んできました。
これは神様が祝っている証とのこと。
昨年3月には公民館も新しく立て替えを行い、獅子も新しくなったうるま市江洲地区。
これから益々の発展をお祈りしております。
2018年07月30日 15:13





再生~トリスケル≫
本当に久々の更新となりました。
ネットと距離を置き、制作に集中したいと思ってから一年。
今また新たな場所に立っているのを感じます。
新しい楽器が生まれてきています。
ことのは
しいの木・スチール弦・ペンタトニック9弦
ナチュラル仕上げ
2018年7月13日(旧6月1日新月・日食)
¥65,000(税別・木製ケース・調弦器込み)
ことのは
しいの木・ガット弦・ペンタトニック9弦
摺り漆仕上げ
2018年7月28日(旧6月15日満月・月食)
¥75,000(税別・木製ケース・調弦器込み)
*売約済み
この3月末~4月、ドイツを訪れ、
ザーレム工房にてホルスト・ニーダー氏から弦製作の研修を受けてきました。
そのことについてはこのブログでも追々書いていきたいと思います。
2017年07月07日 12:04



ちいさな竪琴と歌う季節の歌≫

今日は七夕ですね。
嬉しいお知らせがあります。
楽音の部屋ハーモニーを主催する知花洋子先生が素敵な本を出版されました。
その名も『ちいさな竪琴と歌う季節の歌』。
ペンタトニックの竪琴で四季折々の歌がやさしいパステルの絵とともに紹介されています。
(てるる詩の木工房のちいさな竪琴『ことのは』も表紙に!)
ページをめくるだけでもやさしい気持ちになります。
ちょっとだけ中身を拝見!
知花先生との出会いはもう10年近く前になります。
その当時竪琴を作り初めて間もなく、購入して頂いた楽器に接着のはがれという
あってはならないことが起きました。
木の乾燥や性質を読み切れていなかったことを深く反省し、
作り直しを視野に入れてご連絡しました。
ところが・・・車から降りた知花先生はニコニコしているのです。
『私は障がいをもったお子さんのクラスでもライアーを教えています。
きっとこの子(竪琴)が私の元に来てくれたのは何か縁があると思って。
この楽器の音がとても好きなので交換ではなくて直して頂けないですか?』
怒られて当然だと思っていた私たちにこんな優しい言葉を掛けて下さいました。
(その後修理して今でも弾いて頂いています。)
そんな知花先生の初出版を記念して那覇市のジュンク堂でイベントが
8月19日(土)16:00~17:00に行われるそうです。
ライアー(竪琴)の演奏やこの本にもでてくる小さな楽器の紹介等もあるそうです。
どうぞ興味のある方は予定をチェックされて下さいね。
『ちいさな竪琴と歌う季節の歌』
知花洋子著・高見久美イラスト・編
価格・1500円+税
ご購入希望の方は
知花洋子先生HP http://rakuty.sblo.jp/
沖縄県那覇市のジュンク堂書店
※てるる詩の木工房でも取り扱っております。どうぞお問い合わせ下さい。
さて今日は七夕。
たなばたは『田畑』に通じ、稲の開花、豊作を願い織物を捧げる行事だったそうです。
竪琴の弦もまるで機織りの糸のよう。
奏でることによって美しい布が織られていくようです。
この日、技芸の上達を願う日、とされてきました。
もし忙しい毎日、最近弾いていない・・・という方がいらっしゃいましたら
星空を仰ぎながら竪琴を弾いてみてはいかがですか。
2017年07月04日 19:55



てるる41弦制作①≫
台風の風が運んでいったのか今日は快晴。
沖縄は本格的な夏です。
梅雨明けのこの時期は空気がとても澄んでいて美しい。
紅型作家の友人は毎年この時期にスケッチ旅行をするそうです。
一年に一度だけの色も形も全てがくっきりと見える日。
竪琴は静けさを聴く楽器、といわれています。
喧噪から離れ静けさの中にいるとき耳が開かれていくのだそうです。
聴くとは勝手に音が耳に入ってくることではなく
自分の内側が共鳴し響き合う体験。
沖縄のわらべうたのなかでは子ども達が虫や雨や夕焼けや波に
まるで友達のように歌いかけて自然と共鳴しあっていますね。
かつては農作業の合間にどこからともなく歌声がきこえ、
それに即興で歌が返されていた・・・そんな美しい光景を思います。
(アメリカ独立記念日なので今日は戦闘機が飛ばない!と後で気づきました。)
はちみつとしょうがでうっすら甘みをつけました。
2017年06月22日 18:48






夏至南風≫
季節は巡り沖縄は梅雨明け、心地よい夏至南風が新たな気持ちにさせてくれました。
思うところあってSNSをやめたある日、
毎日見ていたはずのこの幼虫にドキリとしました。
幼虫からさなぎになりやがて成虫になる蝶は変容のシンボル。
自然がたくさんのサインを送っているのに鈍感になっていた気がしたのです。
夏至の昨日、今年も次男が梅を漬けてくれました。
部屋いっぱいに梅の香り!一年の元気のもとです。
海水をくみ上げる美しい砂浜ではヤドカリと出会いました。
久々の太陽の光が気持ちよかったです。
2016年12月25日 13:12


ことのは 2016-12-しいの木-5 2016-12-伊集-2 

冬至生まれのことのは≫
この日、2台のことのはに弦を張りました。
今年仕上がる最後の竪琴となりました。
冬至は太陽が『若太陽』に新しく生まれ変わる日とされ、
沖縄では光の弱まる太陽に歌や踊りを捧げました。
あかあかと上る太陽に手を合わせていると
いろいろな思いがわき上がってきて、それでいてまっさらな不思議な気持ちになります。
11月に来沖された竪琴奏者のスザンネ・ハインツさん。
彼女を浜比嘉島にお連れして砂浴をした時、
『I feel four elements』(四大元素を感じる)とおっしゃっていました。
海の波に水を、砂浜に土を、潮風に風を。
では火は何だろう?とワクワクして聞いていると『warm』。
自然のままの浜辺で砂の中にもぐっているとき、
ご自身の中の温かさに火を感じたのだそうです。
木が葉を落として眠りに入り、
太陽の弱まるこの季節。
より自分の中の太陽に出会えるような気がします。
小さな種のようであってもその温かさや光を持って
新しい年も歩んでいきたいと思います。
どうぞ皆様良い年をお迎え下さい。
2016年11月16日 20:13



旧10月1日生まれのことのは≫
ことのは 2016-10-しいの木-4
新月の日、新しいことのはに弦を張りました。
月の写真を撮る時間が無かったのですが、
次の日の朝愛犬ブランカと散歩していると朝日が昇る反対の空には大きな月。
同じように散歩していた女性が話しかけてきて、
「わったーは宗教が無くて祖先崇拝だけどお日様を見ると神様っているかなあ~と思うさ~」。
そして公園の芝生の上一面に数え切れないほどのモンキチョウ!
2016年10月26日 15:21


スザンネ・ハインツ コンサート&セミナーのお知らせ≫

ドイツのライアー(竪琴)奏者であり、自由音楽学校の教師である
スザンネ・ハインツさんが沖縄にやってきます!
ギリシャに起源を持ち、20世紀になってドイツの子どものための治療教育施設で使われるようになり
現代によみがえった竪琴。
スザンネさんの著書『ライアー演奏の入門』(音楽之友社発行)で学ばれた方も多いと思います。

単なる教則本にとどまらず『静けさを聴く』ライアー(竪琴)の本質が語られており
演奏楽器としての可能性を広げてくれる著書です。
ドイツに行かなければお会いできないスザンネ・ハインツさんのコンサート・セミナー・レッスンが沖縄で行われます!
こんな貴重な機会は度々あるものではありません。
是非スザンネさんの音楽世界にふれてほしいと思いお知らせ致します。
★スザンネ・ハインツ ライアーセミナー
2016年10月31日(月) 19:00開演 (料金:1000円)
於:BOOKCAFE&HALL ゆかるひ (那覇市久茂地3-4-10久茂地YAKAビル3F)
お問い合わせ:てぃーだキッズミュージアム TEL:098-944-0502
★Cafe がらまんじゃく7周年記念催事
スザンネ・ハインツ ライアーコンサート
2016年11月3日(木)祝日 12:00~食事 13:30演奏
(料金:大人4500円 中学生以下1500円)※食事込み
お問い合わせ:098-968-8848
★てぃーだキッズミュージアム20周年記念プログラム
スザンネ・ハインツ ライアープログラム
☆コンサート 2016年11月6日(日) (料金:20ユーロ)
14:30開場 15:00開演
☆セミナー 2016年11月5日(土) (料金:10ユーロ)
15:30開場 16:00開演
☆レッスン 2016年10月31日(月)~11月12日(土)
料金:45分 40ユーロ 60分 60ユーロ
於:てぃーだキッズミュージアム (西原町小橋川80)
お問い合わせ:098-944-0502
※料金はユーロの当日レートで計算し、日本円でお支払い頂きます。
定員に達し次第締め切りますので参加されたい方は
お早めにお問い合わせ下さい。
2016年10月21日 21:21


旧9月16日生まれのことのは≫
10月16日は旧9月16日、満月でした。
この日しいの木のことのはに弦を張りました。
てるる詩の木工房で一番小さい竪琴、ことのは。
この楽器はペンタトニック音階、5つの音で出来ています。
この楽器は男の子です。
ここ数日涼しい夕方は夏の間に伸びきった雑草を抜き、畑を耕していましたが
今日は久々に月の上がるのをゆっくりと眺めることができました。
2016年10月03日 14:52




旧9月1日生まれのことのは≫
10月1日は旧9月1日、新月でした。
この日一台のことのはが完成し、弦を張りました。
そしてもう一台のことのはは漆塗装に入りました。
ことのは9弦ペンタトニック・スチール弦
2016-9-しい-2
そしてこの日、首里汀良町の獅子舞へ向かいました。
銅鑼の倍音と、台風の予兆を感じる風に包まれた舞。
終盤になるにつれ、500年を生きる獅子のエネルギーが放たれ目がらんらんと輝くようでした。
汀良の獅子を彫らせて頂いたことを誇りに思います。
また当時高校生だった青年が青年会長として最後の激しい舞をまい、
立派なあいさつをしていたこともとても嬉しかったです。
2016年08月22日 10:52


てるる39弦制作⑦≫
この日月が昇る頃、2台の竪琴が完成しました。
一年近くかかって完成しました。




(スマートフォンも持っていないので)
初めのうちこそ「書類ができない!」「メールが読めない・送れない!」「図面が書けない!」
と焦っていましたがだんだんと「なんだかこの方が気持ちがいい・・・」「集中できるかも」
と手に心が戻ってきた感じがしました。
いろいろな出来事や感覚が切れ切れでなく、自分で感じることの贅沢さ。
そんなとき飲んだ一杯のコーヒー。
それは同じうるま市にある『鉄塔コーヒー』さんです。
私たちにとってはなじみのある「丸中商会」という金物屋さんの
ちょっと先にあります。
ご夫婦で丁寧に手作りの水出しコーヒー機や焙煎機で作るコーヒーは感動です。何も考えずにただただ味わいました。
あまりにおいしい食べ物や飲み物、すてきな音楽や出来事は
批評や分析などせず、うっとり味わいたいのですよね。
その時にはっきり分かりました。
「私はやはり手作りが好きだなあ」と。
なのでこれまで以上にスローな更新になると思いますが
これまで以上に制作に心を注いでいきたいと思っています。
タグ :てるる39弦